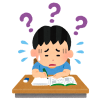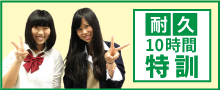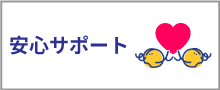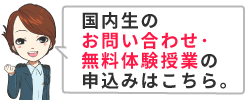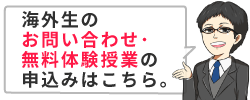現在、教室では一足早く中3、高3の受験カウンセリングと高1、2年生の冬期カウンセリングを実施しています。
受験生はもちろんですが、高1、高2のこの時期は次学年のコースや選択科目を決めていかなければならないので、「将来」を意識せざるを得ません。

「なりたいもの」がないからやる気が出ないの?
よく、カウンセリングの時に保護者様から
「なりたいもの(行きたい学校)が決まらないからやる気が出ないと思うんです」
というような言葉を聞くことがあります。
確かに、「〇〇になりたい!」とか「××大学に行きたい!」という気持ちは行動の原動力になります。とても理想的です。
しかし、この「なりたい」「行きたい」は無理やり作るものではないと思うのです。
子供の「将来の夢」の変化
「〇〇になりたい」という気持ちは年代によってニュアンスが違ってくるような気がするのですよね。
小学校低学年くらいまでは、言っている本人は大真面目、憧れや夢がいっぱいだから、それがとてつもなく現実離れをしていても大人はニコニコ聞いてくれます。
それが、小学校高学年くらいになると「なりたいもの」に大人の期待に対するリップサービスとでも言いましょうか、「こう言ったら喜ぶだろうな」という忖度が入ってくるような気がします。
ちなみに、2020年最新版、小学1年男子がなりたい職業第1位は「スポーツ選手」、第2位は「警察官」。女子は第1位が「ケーキ屋、パン屋」、第2位が「芸能人・歌手・モデル」なんだそうです。まさに夢、憧れですよね。
それが小6になると男子1位は根強い人気の「スポーツ選手」ですが、2位は「医師」。女子は1位が「保育士」、2位が「看護師」です。
堅実なのが悪いと言っているのではなく、なんかつまんないの…。まあ成長したってことなんでしょうがね。
それが中学生になると、夢だろうが忖度だろうがきっぱりとなりたいものが言えなくなる子が出てきます。
「夢」と「現実」
このころになると無邪気に「スポーツ選手!」と言おうものなら、大人から「なれるのは一握りだ」と現実を突きつけられます。昔は笑って「がんばれ!」って言ってたのに…
もちろん子供の方も言われなくてもうすうす気づき始めますしね。
「医者になりたい」と言おうものなら「じゃあ、もっと勉強しろ!」と言われるし…
ヘタに夢を語れば「現実的じゃない」と言われ、「なりたいものがない」と言えばため息をつかれる。どうすりゃいいの?
これはもしかしたらキャリアハラスメント、「キャリハラ」なんじゃないか?
で、“とりあえず”なりたいもの、行きたい学校を決める。
でもとりあえず決めたものには魂がこもっていないから、やる気が出るはずがない。
「なりたいものがない」は悪いことではない!
私はなりたいもの、行きたい学校がないなら「ない」でいいんじゃないかと思います。
「ない」からこそ「なんにでもなれる」。無限の可能性があると考えた方がワクワクしませんか?
私は昔から生徒に「なりたいものがないのなら、学歴をつけろ。」と言ってきました。
学歴はすべてではないけれど、手に職がついているわけでもなく、資格を持っているわけでもないのであれば、自分が何者なのかの証明書にはなりえると思うから。
なりたいものがないからこそ、どんどん動こう!
行きたい高校がなければ自分の力の届く一番高い学校を目指してみればいい。目指しているうちに、レベルはちょっと低いけれど魅力的な学校が出てくれば、そこに行けるわけだから。
なりたいものがないことに後ろめたさを感じながら、行動を起せないくらいなら、ないからこそいろいろな情報に触れ、自由に柔軟に動いていけばいいと思います。
だから、大人は「何になりたいの?」と問いかけるだけではなく、役に立つ立たないを抜きにして、子供たちと世の中の面白そうな情報を交換、共有することが大事なのではないでしょうか。